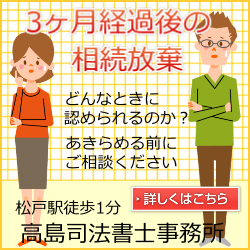相続放棄が出来る期間(3ヶ月の熟慮期間の始期)
 相続放棄が出来る期間は法律により決まっています。
相続放棄が出来る期間は法律により決まっています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければならないと定められています(民法915条1項本文)。
上記の3ヶ月の期間のことを熟慮期間といいます。熟慮期間内であれば、相続を承認するか放棄をするかは自由に選択できるわけですから、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすれば理由はどうであれ受理されます。
しかし、熟慮期間を経過後に相続放棄の申述をした場合には、却下されてしまいます。そのため熟慮期間がいつ開始したか、つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時の解釈が非常に重要となることがあります。
1.自己のために相続の開始があったこと知った時とは
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因である事実を知り、それによって、自分が法律上の相続人となった事実を知った時です。
この時期については、相続人が配偶者または子である場合と、直系尊属や兄弟姉妹である場合とを分けて考える必要があります。
1-1.相続人が配偶者または子である場合
「相続開始の原因である事実」とは、被相続人が死亡した事実を指します。そして、配偶者や子は、被相続人の死亡と同時に相続人となりますから、「自分が法律上の相続人となった事実」を知るのも、被相続人が死亡の時です。
よって、相続人が配偶者または子である場合には、被相続人の死亡の事実を知った時から、熟慮期間である3ヶ月間が開始することになります。
上記の解釈により、被相続人の死亡の事実を知らなければ、どれだけ時間が経っても熟慮期間は開始しないことになります。たとえば、実の親子であっても、まったくの音信不通となったままになっていることもあります。このような場合、債権者からの通知などにより、被相続人の死亡の事実を知ったとすれば、その時から3ヶ月間の熟慮期間がスタートするわけです。
ただし、客観的に見れば、被相続人の死亡のときから3ヶ月間が経過しているのは事実です。そこで、相続放棄の申述をするに際しては、自己のために相続の開始があったことを知った時がいつであるかのを、しっかりと裁判所に伝える必要があります。
そこで、裁判所へ相続放棄申述書を提出する際には、具体的な事情説明書や、説明資料などもあわせて出すのがよいでしょう。
1-2.直系尊属や兄弟姉妹である場合
「相続開始の原因である事実」が、被相続人が死亡した事実を指すのは、相続人が配偶者または子である場合と同様です。
ところが、直系尊属や兄弟姉妹である場合には、「自分が法律上の相続人となった事実」を知るのが、被相続人が死亡の時と一致するとは限りません。
まず、被相続人に子がいなければ、被相続人の死亡と同時に、直系尊属が相続人となります。よって、「自分が法律上の相続人となった事実」を知るのは、被相続人の死亡の事実を知った時と一致しますから、相続人が配偶者または子である場合と同じです。
ところが、被相続人に子がいる場合、被相続人が死亡しても、ただちに第2順位相続人である直系尊属が相続人となることはありません。子が相続放棄をした場合に、その時になってはじめて、直系尊属が相続人となるわけです。
つまり、この場合には、先順位相続人が相続放棄したことを知った時が、「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時となり、その時から熟慮期間がスタートするのです。
もしも、先順位相続人が相続放棄しても、そのことを後順位の相続人に知らせていなかったとします。子の場合、先順位相続人が相続放棄したことを知った時から、3ヶ月の熟慮期間が開始するわけです。
ある人が相続放棄をした場合に、それが後順位の相続人に通知されるような仕組みはありません。そのため、とくに兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となるような場合には、先順位者が相続放棄申述をした事実を知らずにいることもあるでしょう。
この場合でも、相続人が配偶者または子である場合で述べたのと同じように、なぜ、先順位相続人が相続放棄をしてから3ヶ月が経過した後に相続放棄をするのか、事情を説明する必要があります。
2.特別な事情がある場合の熟慮期間の始期
相続放棄ができるのは、相続開始の原因である事実を知り、それによって自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月であるのが原則です。ところが、特別な事情があるときの熟慮期間の始期について、次の最高裁判決があります。
相続人において相続開始の原因となる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時から起算するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日判決)。
3.相続財産の存在を一部でも知っていた場合
上記の最高裁判決は、熟慮期間の起算点の考え方についての基準となるものですが、この判例によれば相続財産が全く存在しないと信じたことが熟慮期間の起算点が後に繰り延べられるための要件の一つとなっています。
それでは、相続人が相続財産の存在を一部でも認識していたときには、熟慮期間の開始時期が後に延びることは絶対に無いのでしょうか。