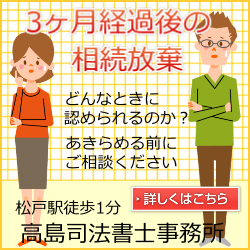相続財産の存在を一部でも知っていた場合(熟慮期間の始期)
最高裁昭和59年4月27日判決では、次のような特別な事情がある場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から、熟慮期間の3ヶ月が開始するとされています。
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。
- 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある。
- 相続人において、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある。
上記判例では「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた」ことを、特別な事情を満たす要件の一つにしています。そうであれば、相続財産が少しでもあることを知っていた場合には、熟慮期間の開始時期が後に延びることは絶対に無いのでしょうか。
家庭裁判所での相続放棄申述受理の審査
相続人が相続財産の存在を一部でも認識していたときであっても、後になって予想外に多額の債務が判明したような場合では、相続放棄の申述が受理される傾向にあります。
家庭裁判所の実務においては、相続放棄申述を受理するための実質的要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するものとして処理されています。東京高等裁判所平成22年8月10日決定では、次のような判断が示されています。
相続放棄をすることができる期間の始期を定める民法915条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったこと及び相続財産の一部又は全部の存在を認識し若しくは認識し得べき状態になった時」と解するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁参照)。
もっとも、相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される。
相続放棄の申述が受理がされても、それが実体要件を備えていることが確定されるものではないので、後で訴訟手続きにおいて争うことができます。したがって、「家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理する」としても、債権者の権利が一方的に損なわれることはないわけです。
相続放棄申述受理の実例
上記のとおり、相続人が相続財産の存在を一部でも認識していたときであっても、後になって予想外に多額の債務が判明したような場合では、相続放棄の申述が受理される傾向にあります。しかし、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた」かどうかを重視している裁判例もあり、下級審でも判断が分かれているところです。
下記の2つの事例は、いずれも遺産分割協議をした後になって、相続債務の存在が発覚したために、それから相続放棄をしようとしたものです。同じような事例であるのに、正反対の結論が出ていることに注意が必要です。
「相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になって初めて、相続の開始を知ったといえる」との主張に対し、被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で他の相続人全員と協議したことをもって、「被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものであり、抗告人らが被相続人に相続すべき財産がないと信じたと認められないことは明らかである」として、相続放棄申述の却下に対する即時抗告を棄却した事例(東京高等裁判所平成14年1月16日決定)。
「相続人が相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と相続人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」として、相続放棄の申述を却下した原審判を取り消して、更に審理を尽くさせるため差し戻した事例(大阪高等裁判所平成10年2月9日決定)。
(最終更新日:平成25年5月4日)