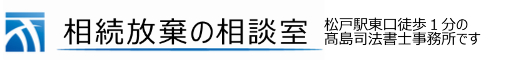このページでは、相続放棄の手続きに関する情報と知識のすべてをご提供することを目的とします。当事務所への相続放棄手続きのご相談・ご依頼については、ご相談予約・お問い合わせ、ご依頼の流れのページなどをご覧ください。
相続放棄の相談室ウェブサイトは、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所では2002年に千葉県松戸市で新規開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。3ヶ月経過後の相続放棄申述についても豊富な経験と実績があります。
事務所へお越しいただいてのご相談・お見積もりは無料で承っています(手続きのご依頼を前提とせず、相談のみをご希望の場合を除く)。すべてのご相談へ司法書士高島一寛が直接対応しておりますのでご安心ください。ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。
1.相続放棄とは
1-1.誰が相続人になるのか
1-2.相続の単純承認、限定承認、相続放棄の選択
2.相続放棄の手続き
2-1.相続放棄手続きの流れ
2-2.相続放棄が出来る期間
2-2-1.自己のために相続の開始があったこと知った時とは
2-2-2.特別な事情がある場合の熟慮期間の始期
2-2-3.相続財産の存在を知っていても、相続放棄が認められた例
2-2-4.相続人が数人いる場合の熟慮期間の起算点
2-2-5.相続人に錯誤があった場合の熟慮期間の起算点
2-3.法定単純承認
2-3-1.相続財産の処分
2-3-2.熟慮期間の経過
2-3-3.相続財産の隠匿など
3.相続の承認・放棄の期間伸長
4.相続放棄の無効・取消し
4-1.相続放棄の撤回
4-2.相続放棄の取消し
4-3.相続放棄の無効
4-4.相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
5.事実上の相続放棄
6.相続放棄の各種情報
6-1.被相続人の生前に相続放棄できるか
6-2.包括遺贈の放棄はできるのか
6-3.一部の相続人が相続放棄した場合
6-4.相続人の全員が相続放棄した場合
6-5.相続人の全員が相続放棄した場合の財産管理
6-6.家庭裁判所における相続放棄申述受理の審理について
6-7.遺産分割協議後の相続放棄申述
7.相続放棄は誰に相談・依頼するのか
8.相続放棄の手続きは高島司法書士事務所へ
1.相続放棄とは
誰が相続人になるかは法律(民法)により定められています。そして、相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。被相続人の「財産に属した一切の権利義務」を承継するということは、つまり、被相続人に債務(負債、借金)があった場合には、その債務も相続人に引き継がれるわけです。
ただし、相続人には「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を引き継ぐかどうかについての選択権を持っています。ある人について相続が開始したとき、その相続人は、相続の単純承認、限定承認、または相続放棄の3つからいずれかを選ぶことができるのです。
そして、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、被相続人が負っていた債務(負債、借金)を引き継ぐことも無くなるので、相続放棄が選択されるのは、被相続人が債務超過である場合が多いです。
相続人が、相続放棄(または、限定承認)をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。他の相続人に対する意思表示だけでは、相続放棄したことにはなりませんのでご注意ください。
1-1.誰が相続人になるのか(法定相続人)
相続放棄が必要かどうかを検討する前提として、誰が相続人となるのかを正確に把握することが重要です。
まず、被相続人に配偶者(夫、妻)がいるときは、その配偶者は必ず相続人になります。なお、ここでいう配偶者は、法律婚の夫婦に限られ、内縁(事実婚)の夫婦は含まれません。つまり、夫婦が内縁の関係である場合、互いに相続人になることは無いわけです。
そして、被相続人の子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹などが次の順位で相続人になります。このとき、被相続人に配偶者がいれば、その配偶者と共に子(または、直系尊属、兄弟姉妹)が相続人となり、配偶者がいなければ子(または、直系尊属、兄弟姉妹)が単独で相続人になるのです。
第1順位 被相続人の子
第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母 ・・・)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
前の順位の相続人がいる場合、後順位者は相続人になりません。たとえば、被相続人に子がいる場合、その子が相続人となりますから、次順位である直系尊属は相続人とはなりません。また、子がいない場合でも、子の代襲相続人がいるときには、直系尊属は相続人となりません。
そして、子(および、その代襲者)がいなければ直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人になります。
なお、配偶者はいるが、第1順位から第3順位相続人のいずれもいない場合には、配偶者のみが相続人です。また、配偶者がいない場合、第1、第2、第3順位相続人のいずれかがいれば、単独で相続人となります。配偶者も、第1、第2、第3順位相続人のいずれもいない場合には、相続人不存在となります。
同順位の相続人の全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人がいれば、順に相続人となります。そして、相続人に当たる人の全員が相続放棄をしたときには相続人不存在の状態となります。
代襲相続について
相続人となるはずであった子が、被相続人の相続開始以前に亡くなっているときには、代襲相続(だいしゅうそうぞく)が生じます。この場合、その死亡している子の子(被相続人の孫)が代襲者として相続人となります。
お、代襲相続が生じるのは、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときのほか、相続人の欠格事由に該当し、または廃除によってその相続権を失ったときです(被相続人の子が相続放棄した場合に代襲相続が生じることはありません)。
さらに、代襲者が相続の開始以前に死亡し、または、相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によってその代襲相続権を失った場合には、その代襲者に子がいれば相続人となります(再代襲)。
また、相続人となるはずの兄弟姉妹が、被相続人の相続開始以前に亡くなっているときなどにも、子の場合と同様に代襲相続が生じます。ただし、兄弟姉妹については再代襲はしないので、相続人になることがあるのは、兄弟姉妹の子(被相続人のおい、めい)までとなります。
1-2.相続の単純承認、限定承認、相続放棄の選択
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないとされています(民法915条)。限定承認または相続放棄をしようとするときは、3か月以内に手続きをしなければならないわけです(単純承認を選択するときは何らの手続きも必要としません)。
(1) 単純承認
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します(民法920条)。
そこで、単純承認した相続人は、被相続人に属していた権利義務のすべてをその法定相続分に応じて引き継ぐことになります。相続を単純承認をするには何らの手続も不要です。自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過することで、自動的に単純承認をしたものとみなされるわけです。
また、上記の3か月の期間(熟慮期間)が経過しなくても、相続財産を処分したときなどには相続を単純承認したものとみなされます。このように一定の事由に該当すると自動的に単純承認したものとみなされるのを法定単純承認といいます。単純承認した後になって、相続放棄や限定承認をすることはできません。
(2) 限定承認
限定承認とは「相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をする」ことです(民法922条)。
限定承認した場合には、債務の弁済や相続財産の換価など相続財産の清算手続を法律にしたがっておこないます。そして、すべての債務を支払ってもまだ残余財産がある場合にのみ、限定承認者はその残余財産を引き継ぐことができます。
上記のとおり、限定承認をすれば、被相続人が債務超過であった場合でもその相続財産の範囲内で債権者への支払いをすれば済むのですが、手続きが複雑なこともあり利用件数は多くありません。裁判所の統計によれば、平成23年には相続放棄の新受件数が166,463件だったのに対し、限定承認はわずか889件に過ぎません。
つまり、被相続人に債務があるときは、大多数の場合に相続放棄が選択されているわけです。限定承認を選ぶべきなのは、プラスの財産も多いが債務もかなりの額になると予想されるような場合に限られることになります。債務があるのかどうか現時点では分からないから、とりあず限定承認をしておくというな選択の仕方は適切ではありません。
(3) 相続の放棄
相続放棄をした人は、その相続については最初から相続人で無かったものとみなされます(民法939条)。相続人ではないのですから、被相続人の債務を支払う義務を負うこともありません。したがって、被相続人が債務超過の状況にあり、その債務を引き継ぎたくないと考える場合には、相続放棄を選択することになります。
ただし、相続放棄した場合には、被相続人が保有していたプラスの財産についても一切引き継ぐことはできなくなりますから注意が必要です。相続放棄をするときでも、財産価値がないものを形見分けとしてもらう程度であれば差し支えありません。しかし、一般経済価値を有する物をもらうのは、相続財産の処分であるとして相続を単純承認したとみなされることになります。
また、いったん家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された後には、その相続放棄を撤回(取消し)することはできません(詐欺や脅迫などによる場合を除く)。したがって、相続放棄を選択する際には、被相続人の財産、債務の状況などをしっかり調査してから慎重に判断すべきです。
2.相続放棄の手続き
相続放棄をすることができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条)。この3か月の期間内に、相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。
相続放棄をするには、3か月の法定期間内に、家庭裁判所で手続きをする必要があるわけです。つまり、期間を過ぎての相続放棄は認められませんし、また、家庭裁判所で手続きをしなければ、法律上の意味での相続放棄の効果は生じません。
民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
民法第938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
2-1.相続放棄手続きの流れ
(1) 申立準備(必要書類の収集・作成)
相続放棄をするには、被相続人の戸籍(除籍)謄本、除住民票、相続人の戸籍謄本などを用意する必要があります。これらの必要書類を集めたら、相続放棄申述書の作成をして家庭裁判所へ提出します。
相続開始から3ヶ月間が経過してから相続放棄申述をする場合などは、上申書(事情説明書)やその他の説明資料もあわせて提出するのがよいでしょう。司法書士に手続きをご依頼いただいた場合には、書類の収集や作成、裁判所への提出などをすべておまかせいただくことができます。不安を感じることなく手続きを進めるためには、最初から司法書士に相談されることをおすすめします。
(2) 家庭裁判所への申立
家庭裁判所へ相続放棄申述受理の申立てをします。申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、管轄裁判所が遠方にある場合でも、お住まいの近くなど他の裁判所へ申立てをすることはできません。
司法書士に手続きをご依頼いただいた場合には、裁判所への申立ても司法書士がおこないますから、申述人ご自身が裁判所へ行く必要はありません。申立後の裁判所とのやり取りも郵送によりますから、通常は一度も裁判所へ行くことなしに相続放棄の手続きが完了します。
裁判所への申立てを司法書士が代行する場合、必要に応じて書類の提出を郵送によりおこないます。そのため、全国どこの家庭裁判所への手続きであっても出張費用等をご請求することはありません。
(3) 裁判所からの照会(問い合わせ)
申立てをおこなった後に、家庭裁判所により審理がおこなわれることになりますが、その際、申述人に対する照会(問い合わせ)があるのが通常です。この照会は文書による場合が多く、その際は、家庭裁判所から照会書(および回答書)ご自宅に郵送されてくるので、同封の「回答書」に必要事項を記入して返送します。
申立をしてから、照会書が送られてくるまでの期間は早ければ1週間程度ですが、申立先の家庭裁判所によっては1ヶ月くらいかかることもあります。家庭裁判所で受付がされていれば、その後の、期間は関係ありませんから心配は不要です。
回答書へは、事実のとおりにありのままに書けばよいのですが、相続放棄申述書と矛盾しないように記入することが大切です。当事務所にご依頼くださった場合には、司法書士が照会書の内容を事前に確認したうえで、書き方についてのご説明をしています。そこで、照会書に記入する前にご持参いただくか、または、メールやファックスでお送りいただいております。
お近くの司法書士事務所に依頼しようとするときは、申立書の作成や提出だけでなく、回答書の記入の仕方などについても指導が受けられるのか確認してからにするのをお勧めします。
(4) 相続放棄申述受理通知書の受領
回答書を返送した後に、家庭裁判所では相続放棄申述を受理するかどうかの審理がおこなわれ、受理された場合には「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。このとき、相続放棄申述受理証明書の交付申請書も同封されているのが通常なので、必要に応じて交付請求をします。
なお、相続放棄申述受理通知書があれば相続放棄の申述が受理されたことは明らかなので、相続放棄申述受理証明書は多くの場合不要です。ただし、不動産相続登記の際など、相続放棄申述受理通知書ではなく、申述受理証明書の添付が求められる手続きもあります。
判明している債権者などがある場合には、必要に応じて相続放棄申述受理通知書のコピーなどを送付します。当事務所へご依頼いただいている場合には、債権者などへの通知も司法書士におまかせいただけますから安心です。
2-2.相続放棄が出来る期間
上記のとおり、相続放棄が出来る期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。この3か月の期間のことを熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。
熟慮期間内であれば、相続を承認するか放棄をするかは相続人が自由に選択できます。したがって、相続人が自らの意思で熟慮期間内に申述をすれば、相続放棄は必ず受理されることとなります。
けれども、何らの手続きをしないうちに熟慮期間を経過すれば、その時点で相続を単純承認したものとみなされてしまいます。その後になって、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしても却下されてしまうのが原則です。
そのため、熟慮期間がいつスタートしたか、つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時がいつであるのかの解釈が、相続放棄が受理されるかどうかの判断において非常に重要となることがあります。
2-2-1.自己のために相続の開始があったこと知った時とは
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、「相続開始の原因である事実」を知り、それによって、「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時であるとされています。この2つの事実を知った時期については、相続人が配偶者または子である場合と、直系尊属や兄弟姉妹である場合とを分けて考える必要があります。
(1) 被相続人の配偶者または子が相続人である場合
1つの目の「相続開始の原因である事実」とは、被相続人が死亡した事実のことです。そして、被相続人の配偶者および子は、被相続人の死亡と同時に相続人となりますから、2つ目の「自分が法律上の相続人となった事実」を知るのも、被相続人が死亡した事実を知った時と同時です。よって、被相続人の配偶者または子については、被相続人の死亡の事実を知った時から、熟慮期間である3ヶ月間が開始することになります。
ここで重要なのは、被相続人が死亡したときから熟慮期間がスタートするのではなく、あくまでも、死亡の事実を知った時が熟慮期間の始期であるということです。つまり、被相続人が死亡しても、その事実を知らないでいたとすれば、相続開始からどれだけ時間が経っていたとしても熟慮期間は開始しないことになります。
たとえば、実の親子であっても、両親が離婚したことなどによって、長年に渡り全く交流がないのは決して珍しいことではありません。また、長年別居しており夫婦関係が破綻していたとしても、戸籍上は夫婦のままなのであれば、当然に相続人となります。このような場合、被相続人が死亡してもその事実を知らないことも考えられますが、その後、債権者からの通知などにより被相続人の死亡の事実を知ったとすれば、その時から3ヶ月間の熟慮期間がスタートするわけです。
ただし、客観的に見れば、被相続人の死亡の時から3ヶ月間が経過しているのは事実です。そこで、相続開始から3か月以上が経過した後に、家庭裁判所へ相続放棄申述をするに際しては、自己のために相続の開始があったことを知った時がいつであるかのを、しっかりと裁判所に伝える必要があります。そこで、相続放棄申述書を提出する際に、具体的な事情を書いた上申書(事情説明書)や、説明資料なども一緒に提出するのがよいでしょう。
(2) 直系尊属や兄弟姉妹が相続人である場合
「相続開始の原因である事実」が、被相続人が死亡した事実を指すのは、相続人が配偶者(または子)であるときと同様です。しかし、直系尊属や兄弟姉妹である場合には、「自分が法律上の相続人となった事実」を知るのが、被相続人が死亡した時と同時であるとは限りません。
まず、被相続人に子がいなければ、被相続人の死亡と同時に直系尊属が相続人となりますから、相続人となる直系尊属が「自分が法律上の相続人となった事実」を知るのは、被相続人の死亡の事実を知った時と同時です。よって、この場合には、相続人が配偶者(または子)であるときと同じく、被相続人の死亡の事実を知った時から、熟慮期間である3ヶ月間が開始することになります。
ところが、被相続人に子がいる場合には、被相続人が死亡した時点では、第2順位相続人である直系尊属が相続人となることはありません。そして、第1順位相続人である子の全員が相続放棄をしたときになって、はじめて直系尊属が相続人となるわけです。つまり、この場合には、先順位相続人の全員が相続放棄したことを知った時が、「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時となり、その時から3か月の熟慮期間がスタートするのです。
また、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)については、第1順位相続人(被相続人の子、またはその代襲者)、第2順位相続人(直系尊属)がいる場合には、その全員が相続放棄をしなければ相続人になることはありません。したがって、第1順位および第2順位相続人の全員が相続放棄したことを知った時が熟慮期間の始期となります。
ここで注意すべきは、熟慮期間の起算点は「先順位相続人の全員が相続放棄した時」ではなく、「先順位相続人の全員が相続放棄したことを知った時」であることです。ある人が相続放棄をした場合に、それが後順位相続人に通知されるような仕組みは存在しません(裁判所から通知が行くこともありません)。
そのため、とくに兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となるような場合には、先順位者が相続放棄をした事実を知らずにいることも多いです。この場合、先順位者が相続放棄したことを知った時から3ヶ月以内であれば、被相続人の死亡からどれだけ期間が経過していても相続放棄が可能であるわけです。
ただし、先順位相続人が相続放棄してから3ヶ月間が経過している場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時(先順位者が相続放棄したのを知った時)がいつであるかのを、しっかりと裁判所に伝える必要があります。そこで、裁判所へ相続放棄申述書を提出する際には、具体的な事情説明書や、説明資料などもあわせて出すのがよいでしょう。
2-2-2.特別な事情がある場合の熟慮期間の始期
相続放棄ができるのは、相続開始の原因である事実を知り、それによって自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月であるのが原則です。しかしながら、上記各事実を知った時から3か月が経過しているときであっても、特別な事情が存在する場合の熟慮期間の始期について判断を示した、次の最高裁判決があります。
相続人が、相続開始の原因たる事実、およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認、または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。
上記の最高裁判決では、「相続財産が全く存在しないと信じたこと」、そして、「このように信ずるについて相当な理由がある」のが必要条件としています。この条件を満たしているときには、相続人が「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時」から熟慮期間がスタートするとしています。
この判例は、現在においても熟慮期間の起算点の考え方についての基準となるものですが、相続財産が全く存在しないと信じたことが前提条件になっていますから、それを厳密に捉えれば、相続財産が少しでも存在すると知っていたときには、それを知った時点で熟慮期間がスタートしてしまうことになります。
そうであれば、相続が開始した時点で、相続人が相続財産の存在を一部でも認識していたときには、熟慮期間のスタート時期が後に繰り延べられることは絶対に無いのかといえば、実際にはそのような取り扱いはされていません。現実には、相続人が相続財産の存在を一部でも認識していたときであっても、後になって予想外に多額の債務が判明したような場合では、債務の存在を知ったときから3ヶ月間以内の相続放棄の申述が受理される傾向にあるのです。
2-2-3.相続財産の存在を知っていても、相続放棄が認められた例
相続財産の存在を知っていても相続放棄が認められた例として、相続財産が存在することを前提にして遺産分割協議をしたものの、その後に多額の保証債務が発覚したケースで「遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」として、相続放棄の申述を却下した原審判を取り消して、更に審理を尽くさせるため差し戻した裁判例があります。
相続人が相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と相続人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある(大阪高等裁判所平成10年2月9日決定)。
遺産分割協議をするのは、相続の法定単純承認事由である「相続財産の処分」に当たります。この決定では「他の共同相続人との間で遺産分割協議をしており、右協議は、相続人らが相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきである」とした上で、上記の決定をしています。
したがって、相続債務の不存在を誤信しても仕方の無い事情があるときには、相続財産の存在を認識していても、後から相続放棄が可能な場合があることになります。これは、熟慮期間について次のような判断を示していることからも明らかだといえます。
民法915条1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3か月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであり、かつそのように信ずるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算するべきものと解するのが相当である。
ただし、上記裁判例において判断の対象となっているのは、遺産分割協議により遺産を取得しないとした相続人です。遺産を取得した相続人については、上記裁判例の判断には含まれないと考えるべきでしょう。また、上記裁判例と同じように、遺産分割協議をした後に相続放棄申述をしたケースで、相続放棄申述の却下に対する即時抗告を棄却した裁判例があります。
相続人による「相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になって初めて相続の開始を知ったといえる」との主張に対し、被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で他の相続人全員と協議した事実をもって、「被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものであり、抗告人らが被相続人に相続すべき財産がないと信じたと認められないことは明らかである」として、相続放棄申述の却下に対する即時抗告を棄却した裁判例があります(東京高等裁判所平成14年1月16日決定)。
この決定では、遺産を取得した相続人だけでなく、相続分不存在証明書に署名押印した相続人の相続放棄申述も却下されています。つまり、遺産分割協議において、遺産を取得しないものとした相続人の相続放棄も認められなかったわけです。
この裁判例は、相続放棄申述却下審判に対する即時抗告事件ですが、抗告人による次のような主張が否定されています。
相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った場合であっても,3か月以内に相続放棄をしなかったことが,相続人において相続債務が存在しないか,あるいは,相続放棄の手続をとる必要をみない程度に少額にすぎないと誤信したためであって,かつ,そのように信ずるにつき相当の理由がある場合には,相続債務のほぼ全容を認識したとき又は通常これを認識すべきときから起算すべきものと解するのが相当である
本決定の立場によれば、「被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識」した時点で、熟慮期間が開始することになりますから、相続債務の不存在を誤信していたなどの事情は全く関係ないことになります。上記と同じような事例にもかかわらず、全く反対の結論となっていますから注意が必要です。
しかしながら、当事務所で実際に取り扱った事件で、遺産分割協議により遺産を取得しないとした相続人による相続放棄申述では、「遺産分割協議をしたとの事実」のみをもってただちに却下されたことはありません。家庭裁判所での相続放棄申述受理の審判について、上記の大阪高決平成10年2月9日で次のような判断も示されています。
申述受理の審判は、基本的には公証行為であり、審判手続で申述が却下されると、相続人は訴訟手続で申述が有効であることを主張できないから、その実質的要件について審理判断する際には、これを一応裏付ける程度の資料があれば足りるものと解される。
・関連する裁判例
(東京高決平成19年8月10日)
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状況その他諸般の事情からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日判決・民集38巻6号698頁)。そして、上記判例の趣旨は、本件のように、相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合にも妥当するというべきであり、したがって、この場合の民法915条1項所定の期間は、相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である。
(名古屋高決平成11年3月31日)
相続人が被相続人の死亡時に、被相続人名義の遺産の存在を認識していたとしても、たとえば右遺産は他の相続人が相続する等のため、自己が相続取得すべき遺産がないと信じかつそのように信じたとしても無理からぬ事情がある場合には、当該相続人において、被相続人名義であった遺産が相続の対象となる遺産であるとの認識がなかったもの、即ち、被相続人の積極財産及び消極財産について自己のために相続の開始があったことを知らなかったものと解するのが相当である。
2-2-4.相続人が数人いる場合の熟慮期間の起算点
「相続人が数人いる場合には、民法915条1項に定める3か月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったこことを知った時から各別に進行するものと解するのが相当である」とされています(最判昭和51年7月1日)。そのため、数人の相続人が同時に相続放棄の申述をした場合に、一部の相続人の相続放棄のみが受理されるということもあります。
2-2-5.相続人に錯誤があった場合の熟慮期間の起算点
被相続人が生前出資し、貯金し、建物更生共済に加入するなどして取引していた農協の支所を訪れ、被相続人の本件農協に対する債務の存否を尋ね、債務はない旨の回答を得た。そこで、相続放棄の必要があるとは考えていなかったのが、後になって、本件農協から債権回収についての通知が届いたため、相続放棄の申述をしたという事例です。
被相続人の消極財産の状態について、熟慮期間内に調査を尽くしたにもかかわらず、被相続人の債権者からの誤った回答により、相続債務が存在しないものと信じたため、限定承認又は放棄をすることなく熟慮期間を経過するなどしてしまった場合には、上記錯誤に陥っていることを認識した後改めて民法915条1項所定の期間内に、錯誤を理由として単純承認の効果を否定して限定承認又は放棄の申述受理の申立てをすることができるとの判断がなされています。
(高松高決平成20年3月5日)
相続人が、自己のために開始した相続につき単純若しくは限定の承認をするか又は放棄をするかの決定をする際の最も重要な要素である遺産の構成、とりわけ被相続人の消極財産の状態について、熟慮期間内に調査を尽くしたにもかかわらず、被相続人の債権者からの誤った回答により、相続債務が存在しないものと信じたため、限定承認又は放棄をすることなく熟慮期間を経過するなどしてしまった場合には、相続人において、遺産の構成につき錯誤に陥っており、そのために上記調査終了後更に相続財産の状態につき調査をしてその結果に基づき相続につき限定承認又は放棄をするかどうかの検討をすることを期待することは事実上不可能であったということができるから、熟慮期間が設けられた趣旨に照らし、上記錯誤が遺産内容の重要な部分に関するものであるときには、相続人において、上記錯誤に陥っていることを認識した後改めて民法915条1項所定の期間内に、錯誤を理由として単純承認の効果を否定して限定承認又は放棄の申述受理の申立てをすることができると解するのが相当である。
2-3.法定単純承認
相続放棄(または、限定承認)ができるのは、「相続人が単純承認したものとみなされる」までの間です。どのような場合に、単純承認したものとみなされるかは、民法921条に次のとおり定められています。
(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条(短期賃貸)に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。→ 相続財産の処分
2 相続人が第915条第1項の期間(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。→ 熟慮期間の経過
3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 → 相続財産の隠匿など
2-3-1.相続財産の処分
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為、および短期賃貸を除く)には、相続を単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。どのような場合に、法定単純承認の効果を生じさせる「相続財産の処分」があったと判断されるかが、相続放棄が認められるかどうかの判断において非常に重要な意味を持つことがあります。
(1) 処分行為とは
ものを処分するというのは、「不要なものや余分なものなどを、捨てる、売り払う、消滅させる、など適当な方法で始末すること」を指します(デジタル大辞泉より)。
「処分行為」とは、財産の現状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為をいいます。売却などの法律行為だけでなく、相続財産である家屋の取り壊しや、動産の毀損などの事実行為も、処分行為に含まれるわけです(なお、相続財産の無償貸与行為については、処分行為にはあたらないとされています)。
被相続人名義の銀行預金を引き出して、相続人が自分のために使ってしまった場合、相続財産の処分にあたるのは明らかだといえます。しかし、被相続人についての葬儀費用の支払い、支払期限が到来した相続債務(被相続人の借金など)の弁済などについては、後に述べるとおり、相続財産の処分にはあたらないと判断されることが多いでしょう。
(2) 保存行為と、相続財産の処分
「保存行為」とは、財産の価値を現状のまま維持するために必要な行為です。相続財産の処分行為をしたときでも、それが保存行為に該当するときには、法定単純承認の効果を生じさせる処分行為には含まれません。
「財産の価値を現状のまま維持する」となれば、限定された行為に限られてしまいますが、期限の到来した債務の弁済、腐敗しやすい物の処分など、財産の全体からみて現状維持のために必要だと認められる行為も処分行為には該当しないと考えられます。
ただし、弁済に回された財産の相続財産中に占める割合が大きいため、一部の相続債権者の権利行使が困難になり、その結果、相続債権者間に不公平をもたらすことを理由に、法定単純承認事由に該当すると判断された例もあります(昭和53年10月23日富山家庭裁判所)。
2-3-2.熟慮期間の経過
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に、相続放棄(または、限定承認)をしなかったときには、単純承認したものとみなされます。熟慮期間がいつから始まるかについては、2-1.相続放棄が出来る期間をご覧ください。
2-3-3.相続財産の隠匿など
相続放棄申述が家庭裁判所に受理された後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費したときには、単純承認したものとみなされます。
相続財産の全部もしくは一部を他人から隠す行為は秘匿にあたります。また、相続財産の消費については、私かに(ひそかに)となっていますが、ほしいままに私物化することを指していますから、こっそりとおこなわれる必要はありません。
なお、上記のような行為がなされたのが、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後であったならば、単純承認したものとみなされることはありません。
たとえば、第一順位相続人である、被相続人の子が相続放棄した後に、相続財産の一部を他人から隠したとします。この場合でも、隠匿行為がおこなわれたのが、後順位の相続人である、被相続人の親が相続を単純承認した後であったなら、法定単純承認の効果は生じないわけです。
相続人間で故人を偲ぶよすがとなる遺品を分配する、いわゆる「形見分け」は、相続財産の隠匿にはあたらないのが原則です。しかし、遺品のほとんどすべてを持ち帰っているのが、いわゆる形見分けを超えるものといわざるを得ないとして、隠匿に該当すると判断された裁判例もあります(東京地方裁判所平成12年3月21日判決)。
3.相続の承認・放棄の期間伸長
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をすることができます。相続人が複数いる場合には、熟慮期間は相続人ごとに別々に進行しますから、期間の伸長は相続人ごとにおこなう必要があります。
相続の承認・放棄の期間伸長の申立は、相続の開始後、熟慮期間を経過する前におこなわなければなりません。相続人が熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき(民法921条2号)は、単純承認をしたものとみなされますから、その後になって期間伸長の申立をすることもできません。つまり、何も手続きをしないでいるうちに熟慮期間を過ぎてしまったとして、その後に、相続の承認・放棄の期間伸長の申立てをしても認められないわけです。
家庭裁判所へ相続の承認・放棄の期間伸長の申立てがされた場合、裁判所では相続財産の構成の複雑性、所在場所、相続人の海外や遠隔地居住の状況などを考慮してその当否を判断するとされています。この期間伸長は各共同相続人について個別に認められるものであり、相続人中の1人について期間伸長が認められたとしても、ほかの共同相続人の熟慮期間には影響しません。
相続の承認・放棄の期間伸長の申立にあたり、申立書へ必要だと考える伸長期間を書くことは出来ますが、家庭裁判所が審判をする際は、その裁量により伸長期間を決定します。また、期間伸長の審判がなされた後、事情によっては再度の期間伸長申立をすることも可能です。再度の期間伸張申立てができるのは、伸長が認められている期間内です。
4.相続放棄の無効・取消し
4-1.相続放棄の撤回
相続の承認及び放棄は、民法915条1項の期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)でも、撤回することができないとされています(民法919条1項)。よって、相続放棄の申述が受理された後には、3か月の熟慮期間内であったとしても、相続放棄を取りやめる(撤回する)ことはできません。
ただし、家庭裁判所へ相続放棄の申述をした後であっても、その申述が受理されるまでの間であれば、相続放棄申述の撤回(取下げ)は認められます。
実際の相続放棄の手続きでは、家庭裁判所へ相続放棄申述書および戸籍謄本などの必要書類を提出した後に、家庭裁判所から申述人に対し照会書(回答書)が郵送されてくるのが通常です。その後、回答書を返答してからしばらしくて、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
回答書を返送してしまえば、程なくして申述が受理されますから、それから相続放棄申述の撤回(取下げ)をするのは難しいかもしれませんが、回答書の返送前であれば問題なく撤回(取下げ)ができるわけです。
民法919条1項の規定に照し、一度受理された相続放棄の撤回は許されない(最判昭和37年5月29日)
4-2.相続放棄の取消し
相続放棄の取消しができるのは次のような場合に限られます。申述人が未成年者、成年被後見人、被保佐人に該当しないときには、相続放棄の取消しができるのは、詐欺または強迫によって相続放棄した場合に限られることになります。
- 未成年者が、その法定代理人の同意を得ずに相続放棄した場合(民法5条)
- 成年被後見人が自ら相続放棄をした場合(民法9条)
- 被保佐人が、その保佐人の同意を得ずに相続放棄した場合(民法13条)
- 詐欺または強迫によって相続放棄した場合(民法96条)
- 後見監督人がいるときに、その同意を得ずに、後見人が被後見人に代わって相続放棄をした場合(民法864条)
- 後見監督人がいるときに、その同意を得ずに、後見人が未成年被後見人が相続放棄することに同意した場合(民法864条)
上記の取消原因がある場合に、相続放棄の取消しをしようとするときには、家庭裁判所に「相続放棄取り消しの申述」をします。相続放棄の取消権は、追認をすることができる時から6か月間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続放棄の時から10年を経過したときも、相続放棄の取消権が時効によって消滅します(民法919条3項)。
4-3.相続放棄の無効
相続放棄の無効について定めた民法の規定は存在しません。けれども、相続放棄が錯誤により無効になる場合があるとされています。
最判昭和40年5月27日
相続放棄は家庭裁判所がその申述を受理することによりその効力を生ずるものであるが、その性質は私法上の財産法上の法律行為であるから、これにつき民法95条(錯誤)の規定の適用がある。
民法95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
相続放棄の申述が受理されていても、その相続放棄に無効原因がある場合には、無効であることについての裁判所への申述等をすることなく、訴訟等で相続放棄の無効を主張することができます。
いったん家庭裁判所において相続放棄の申述が受理されたからといって、相続放棄の効力を確定させるわけではなく、同受理後でも、相続放棄に法律上無効原因があれば、その無効を主張する利益がある者は、相続放棄の効力を争うことができる(福岡高決平成16年11月30日)
また、上記高裁決定において、訴訟等で相続放棄の無効を主張するのではなく、相続放棄が錯誤であることを理由として、相続放棄取消しの申述をすることは許されないと判断されています。
相続放棄の無効事由を主張して、家庭裁判所にその相続放棄の取消しの申述の受理を求めることができないと解しても、相続放棄に法律上無効原因があるとしてその無効を主張する利益がある者は、別途訴訟でそれを主張して争う途が用意されているのであるから、同人に、実体法上も、手続法上も、看過すべからざる格別の不利益をもたらすものではない。換言すれば、実定法上の規定がないにもかかわらず、敢えて、解釈上、民法919条1・3項及び家事審判法9条1項甲類25号の2を類推適用して、相続放棄の無効の申述を受理すべきであるとしなければならない必要性は見当たらない(福岡高決平成16年11月30日)。
上記のとおり、相続放棄の申述が受理されていても、その相続放棄に無効原因がある場合には、訴訟等で相続放棄の無効を主張することができますが、「相続放棄の無効確認」を求める訴訟を提起することはできないと考えられます。
当該相続放棄の無効であることによって、いかなる具体的な権利または法律関係の存在、もしくは不存在の確認を求める趣意であるかは明確でない。相続のごとき複雑広汎な法律関係を伴うものについて、無効確認の対象となるべき法律関係は、少しも具体化されていない(もとより、全般的にかかる相続放棄無効確認の訴を許す特別法規も存在しない。)。すなわち、かかる確認の訴は、適法な「訴の対象」を欠くものといわざるを得ない(最判昭和30年9月30日)。
4-4.相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたとしても、そのことによって相続放棄の効力が終局的に確定するものではありません。たとえば、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたとして、3か月経過後の相続放棄申述が受理されている場合であっても、債権者は別訴(貸金返還請求訴訟、保証債務履行請求訴訟等)によりその効力を争うことができます。
家庭裁判所による放棄申述の受理審判は適式な申述の公証行為に止まり相続放棄の効力の有無を終局的に確定するものではなく、利害関係人間で別訴によりその無効(錯誤、心裡留保、法定単純承認事実の存在等)を争いうる(大阪高決昭和61年10月1日)
家庭裁判所における、相続放棄申述受理の審判での審理はほとんどの場合、申述人から提出された書面のみによります。したがって、事実と違うことが書かれていたとしても、相続放棄申述が受理されてしまうことも十分に考えられます。下記の大阪高裁決定での、家庭裁判所における申述受理審判の審理について示されている判断が参考になります。
申述受理の審判は基本的には公証行為であること及び申述の効力は終局的には訴訟手続で確定されるものであって、審判手続で申述が却下されると相続人は訴訟手続で申述が有効であることを主張できなくなることからして、申述受理の審判での審理は一応のものに止め、その結果、申述の要件を欠くことが明白な場合においてのみこれを却下することができ、そうでない限り申述を受理し、その効力の有無について本格的審理を必要とするときは、判断を訴訟手続に委ねるべきである(仙台高決平成4年6月8日)。
5.事実上の相続放棄
法律上の相続放棄の効力が生じるのは、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されている場合に限られますが、次に掲げるような「事実上の相続放棄」といわれる方法が採られることもあります。
- 遺産分割で、自分は何らの財産を取得しないものとする協議を成立させる。
- 生前贈与を受けているとして、相続分のなきことの証明書(特別受益証明書)を作成する。
- 相続分を特定の相続人に譲渡したり、相続分の放棄をする。
上記のような事実上の相続放棄をした場合、その相続人は財産を取得しませんが、債務については他の相続人と共に相続することに注意が必要です。たとえば、遺産分割協議において、特定の相続人が全ての財産と債務を相続するとの合意をしたとしても、そのことをもって債権者に対抗することはできません。債務から逃れるためには、債権者の同意を得ることが必要とされます。
また、判明している債務については、債権者の同意を得て免責されたとしても、後になって別の債務が発覚した場合には、その債務を承継することになってしまいます。したがって、債務を含めた全財産を特定の相続人に相続させようとするならば、上記のような事実上の相続放棄によるのではなく、家庭裁判所へ相続放棄の申述をするべきです。
さらに、遺産分割協議などにより事実上の相続放棄をした場合、その遺産分割協議をおこなったことが相続財産の処分行為に当たり、法定単純承認事由に該当するとされていることにも注意すべきです。
他の共同相続人との間で本件遺産分割協議をしており、右協議は、抗告人らが相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきである(大阪高決平成10年2月9日)。
6.相続放棄の各種情報
6-1.被相続人の生前に相続放棄できるか
家庭裁判所へ相続放棄の申述ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条)。相続が開始していることが絶対条件ですから、被相続人の生前に相続放棄することはできません。かりに、多額の債務を抱えて債務超過の状態にあり、相続が開始した際には相続放棄するのが確実な場合であっても、生前に相続放棄をすることは認められないのです。
その人に属する権利義務(債権・債務)のすべてが確定するのは死亡のときです。亡くなる瞬間までは財産状況がどう変動するかは分かりません。そして、相続放棄した後になって、その撤回や取消は原則としてできないのですから、生前の相続放棄を認めるべきではないのは当然ともいえるでしょう。
被相続人の生前に「自分は遺産を相続しない(相続を放棄する)」と他の相続人に伝えていたり、更にそれを書面にしているから、自分は相続放棄をしているのだと言われる方もいます。しかし、それは法律上の意味での相続放棄だとは認められません。このような場合であっても、相続開始後に家庭裁判所で手続きをしなければ相続放棄をしたことにはならないのでご注意ください。
遺産の範囲は相続の開始により初めて確定するのであつて、その相続放棄や分割協議の意思表示は、そのとき以後における各相続人の意思によりなさるべきものであるから、当事者間で事前にこれらの意思表示をなすも何らの効力を生じない(横浜地方裁判所川崎支部判決昭和44年12月5日)。
6-2.包括遺贈の放棄はできるのか
包括遺贈とは、遺言により「遺言者の遺産のすべて」、または、「遺言者の遺産の3分の1」のように割合を定めて遺贈することです。不動産など財産を指定して遺贈するのではなく、財産を包括的に遺贈するわけです。包括遺贈を受けた受遺者のことを、包括受遺者といいます。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)とされます。そのため、包括遺贈を受けた割合に応じて、遺言者の財産だけで無く負債(債務)も引き継ぐことになります。そのため、遺言者が債務超過の状況で死亡したような場合には、相続人の場合と同様に、包括受遺者は自らの財産を処分してでも債務を支払う義務を負うことになります。
そこで、包括受遺者には、相続人の場合と同様に相続の放棄・承認についての規定が適用され、包括遺贈の放棄をすることが認められています。したがって、包括遺贈の放棄をするには、自己のために包括遺贈があったことを知ったとき(自分が包括受遺者であることを知ったとき)から3ヶ月以内に、家庭裁判所で包括遺贈の放棄の申述をする必要があります。包括遺贈の放棄の申述をしたときには、包括受遺者としての権利義務は一切なくなりますから、プラスの財産についての遺贈も受けられなくなるのは当然です。
「後記記載の不動産を○○に遺贈する」というように財産を特定しての遺贈が「特定遺贈」です。特定受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986条)。特定遺贈の放棄にはとくに方式の定めはありませんから、遺贈義務者に対して放棄する旨の意思表示をすれば済みます。したがって、家庭裁判所で「特定遺贈の放棄」などといった手続きをする必要はありません。
6-3.一部の相続人が相続放棄した場合
複数いる相続人中の1人が相続放棄をした場合に、その相続人が負担するはずだった債務が消滅することはありません。相続放棄しなかった相続人が、全ての債務を負担することになります。
たとえば、相続債務が100万円だったとして、相続人が配偶者および2人の子だった場合、配偶者が50万円、子がそれぞれ25万円ずつの支払い義務を負担します。このとき、子の1人が相続放棄した場合でも、その子が負担するはずだった25万円の債務が消滅することはなく、債務総額は100万円のままです。
そして、この25万円は放棄しなかった方の子が全額負担することになるので、結局、配偶者が50万円、子が50万円の債務を相続することになります。これは、相続放棄した人は最初から相続人で無かったものとみなされるからです(民法939条)。
つまり、2人いる子のうちの1人が相続放棄した場合、相続人になる子は最初から1人だったものとみなされるので、配偶者と子が2分の1ずつの債務を引き継ぐこととなるのです。
6-4.相続人の全員が相続放棄した場合
同順位の相続人の全員が相続放棄したときには、次順位者が相続人となります。子の全員が相続放棄すれば直系尊属、直系尊属の全員が相続放棄すれば兄弟姉妹が相続人となるわけです。債務の支払い義務から逃れるために相続放棄しようとするときには、後順位者の存在についても把握しておくべきでしょう。
なお、子が相続放棄したことにより、その子の子(被相続人の孫)が相続人になることはありません。相続放棄により代襲相続が生じることはないからです。また、被相続人の父母が相続放棄した場合、祖父母がいれば相続人となります。このときは、相続人になる父母がそもそもいなかったのと同じことになるので、祖父、祖母が相続人となるのです。
被相続人の妻はいつでも相続人となりますが、相続人の順位とは関係ないので、妻が相続放棄したことによって他の人が相続人になることはありません。妻が相続放棄すれば、妻に行くはずだった相続分の全てが、最初から他の相続人に承継されます。
相続人の全員が相続放棄した場合には、相続人がいないこととなります(相続人不存在)。この場合には、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)などの申立により、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が、相続財産の管理をおこないます。
6-5.相続人の全員が相続放棄した場合の財産管理
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされています(民法940条第1項)。
委任契約の場合の受任者の注意義務では、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負うとされています(民法644条)。これに対し、相続放棄者による財産管理では、自己の財産におけるのと同一の注意をもってとされていますから、委任の場合ほどの注意義務は負わないわけです。
しかしながら、民法939条で「相続放棄者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなす」とされているからといって、ただちに財産管理義務が無くなるわけではなく、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」財産管理を継続しなければならないのです。
また、注意しなければならないのは、相続放棄をした後であっても相続財産の処分をおこなってしまえば、相続を単純承認したものとみなされるということです。つまり、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された後でも、単純承認の効果が生じてしまうわけです。
民法921条では「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす」として法定単純承認の事由が列挙されていますが、この3号本文に「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」とあります。
何をしてしまったら「相続財産の隠匿や消費」に当たるのかは判断に困ることもあるでしょうが、おこなうべきはあくまでも「相続財産の管理を継続」することです。
民法940条(相続の放棄をした者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
民法645条(受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
民法646条(受任者による受取物の引渡し等)
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
民法650条(受任者による費用等の償還請求等)
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
第918条(相続財産の管理)
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 第27条から第29条まで(不在者財産管理人の職務、権限など)の規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
6-6.家庭裁判所における相続放棄申述受理の審理について
相続放棄の申述の受理手続きにおける家庭裁判所の審理は、「却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきである」とされています。たとえば、相続開始から3ヶ月間を経過した後の相続放棄申述であり、熟慮期間の始期が後ろの繰り延べられるような特段の事情が存在しないときには、却下すべきことが明らかだといえるでしょう。
けれども、個々のケースによっては、熟慮期間を徒過しているのかが明確でない場合もありますが、このようなときには「却下すべきことが明らかな場合」以外は受理するとの取り扱いがなされているのだと思われます。以下は、相続放棄申述受理の審判についての判断がなされている裁判例を列挙します。
(東京高決平成22年8月10日)
相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される。
(大阪高決平成10年2月9日)
申述受理の審判は、基本的には公証行為であり、審判手続で申述が却下されると、相続人は訴訟手続で申述が有効であることを主張できないから、その実質的要件について審理判断する際には、これを一応裏付ける程度の資料があれば足りるものと解される。
(仙台高決平成8年12月4日)
家庭裁判所が相続放棄の申述を不受理とした場合の不服申立ての方法としては、高等裁判所への即時抗告だけが認められているにすぎず、その不受理の効果に比べて、救済方法が必ずしも十分であるとは言えないから、家庭裁判所において、その申述が熟慮期間内のものであるか否かを判断する場合には、その要件の欠缺が明らかであるときに、これを却下すべきであるとしても、その欠缺が明らかと言えないようなときには、その申述を受理すべきものと解するのが相当である。そして、このように解しても、被相続人の債権者は、後日、訴訟手続で相続放棄の効果を争うことができるのであるから、債権者に対して不測の損害を生じさせることにはならない。
(福岡高決平成2年9月25日)
家庭裁判所は、相続放棄の申述に対して、申述人が真の相続人であるかどうか、申述書の署名押印等法定の方式が具備されているかどうかの形式的要件のみならず、申述が本人の真意に基づいているかどうか、3か月の熟慮期間内の申述かどうかの実質的要件もこれを審理できると解するのが相当であるが、相続放棄申述の受理が相続放棄の効果を生ずる不可欠の要件であること、右不受理の効果が大きいこととの対比で、同却下審判に対する救済方法が即時抗告しかないというのは抗告審の審理構造からいって不十分であるといわざるをえないことを考えると、熟慮期間の要件の存否について家庭裁判所が実質的に審理すべきであるにしても、一応の審理で足り、その結果同要件の欠缺が明白である場合にのみ同申述を却下すべきであって、それ以外は同申述を受理するのが相当である。
(仙台高決平成1年9月1日)
受理審判に当たっては、法定の形式的要件具備の有無のほか、申述人本人の真意を審査の対象とすべきことは当然であるが、法定単純承認の有無、熟慮期間経過の有無、詐欺その他取消原因の有無等のいわゆる実質的要件の存否の判断については、申述書の内容、申述人の審問の結果あるいは家庭裁判所調査官による調査の結果等から、申述の実質的要件を欠いていることが極めて明白である場合に限り、申述を却下するのが相当であると考える。けだし、相続放棄申述受理審判は非訟手続であるから、これによって相続関係及びこれに関連する権利義務が最終的に確定するものではないうえ、相続放棄の効力は家庭裁判所の受理審判によって生じ、それがなければ、相続人には相続放棄をする途が閉されてしまうのであるから、これらの点を総合考慮すると、いわゆる実質的要件については、その不存在が極めて明らかな場合に限り審理の対象とすべきものと解するのが相当だからである。
(大阪高決昭和27年6月28日)
申述の受理は相続放棄の申述のあつたことを公証する行為であって裁判でない。
(最判昭和45年11月20日)
相続放棄の申述の受理は、審判であつても、適式な申述がなされたことを公証する実質のものである。
6-7.遺産分割協議後の相続放棄申述
遺産分割協議をした後に、予期しなかった多額の債務が発覚したような場合において、その分割協議で「遺産を取得しないものとした相続人」による相続放棄申述は、家庭裁判所での審理においては受理される傾向にあると思われます。しかし、同じような事例であっても、遺産を取得しなかった相続人による申述も却下された裁判例もあります。
また、遺産分割協議において「遺産を取得した相続人」による相続放棄申述についても、プラスの財産がごくわずかであり、相続した土地がほとんど無価値であったのに対し、後に判明した債務が多額であったという特殊な事例ですが、当事務所で書類作成をし受理されたことがあります(東京家庭裁判所)。
したがって、遺産分割協議において「遺産を取得した相続人」からの相続放棄申述だからといって、必ずしも却下されるというわけでは無いと思われます。
以下、参考になる裁判例を挙げますが、必要だと思われる箇所のみを抜き出してまとめているものもありますので、実際の判断をするに当たっては全文をご覧になることを推奨します。
(1) 遺産を取得しなかった相続人による申述が受理された事例
「遺産分割協議証明書に署名押印したことが、被相続人の相続財産の不動産についてAの名義に移転登記するためにされたものであり、現実に遺産分割協議がされたものではないから、この書面の送付等をもって、自己のために相続の開始があったことを知ったものと認めることはできない」として相続放棄申述を受理しています。
(東京高決平成26年3月27日)
被相続人が死亡した当時(平成22年8月○日)、被相続人の相続財産に不動産があることを知っていたものの、自己の財産を全て長男Aに譲るとの被相続人の意向を聞いていたために、Aがこの不動産等被相続人の相続財産を一切を相続したので、自らには相続すべき被相続人の相続財産がないものと信じていたことが認められる。
また、被相続人の意向、被相続人と抗告人らとの生前の交流状況からすると、抗告人らが、上記のように信じていたことについて、相当の理由があったことも認められる。
なお、抗告人らは、平成24年2月○日ころ、「遺産分割協議証明書」に署名押印し、Aに送付又は交付したことが認められるが、上記書面は、被相続人の相続財産の不動産についてAの名義に移転登記するためにAに送付等されたものであり、現実に遺産分割協議がされたものではないから、この書面の送付等をもって、自己のために相続の開始があったことを知ったものと認めることはできない(この点に関する経過の詳細等については、訴訟が提起された場合にその訴訟手続内において判断されるべきである。)。
その後、抗告人らは、D信用金庫に問い合わせること等により、平成25年3月○日、AのD信用金庫に対する貸金債務についての連帯保証債務が被相続債務として存在していることを知ったのであるから、本件における熟慮期間の起算日は、抗告人らが前記連帯保証債務の存在を認識した平成25年3月○日とするのが相当である。
「相続財産の一部の物件について遺産分割協議書を作成しているが、これは、本件遺言において当然に長男Aへ相続させることとすべき不動産の表示が脱落していたため、本件遺言の趣旨に沿ってこれをAに相続させるためにしたものであり、抗告人において自らが相続し得ることを前提に、Aに相続させる趣旨で遺産分割協議書の作成をしたものではない」として相続放棄申述を受理しています。
(東京高決平成12年12月7日)
被相続人が死亡した時点で、その死亡の事実及び抗告人が被相続人の相続人であることを知ったが、被相続人の本件遺言があるため、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じたものであるところ、本件遺言の内容、本件遺言執行者である○○銀行の抗告人らに対する報告内容等に照らし、抗告人がこのように信じたことについては相当な理由があったものというべきである。
そのため、抗告人において被相続人の相続開始後所定の熟慮期間内に単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択することはおよそ期待できなかったものであり、被相続人死亡の事実を知ったことによっては、未だ自己のために相続があったことを知ったものとはいえないというべきである。そうすると、抗告人が相続開始時において本件債務等の相続財産が存在することを知っていたとしても、抗告人のした本件申述をもって直ちに同熟慮期間を経過した不適法なものとすることは相当でないといわざるを得ない。
抗告人は、後に、相続財産の一部の物件について遺産分割協議書を作成しているが、これは、本件遺言において当然に長男Aへ相続させることとすべき不動産の表示が脱落していたため、本件遺言の趣旨に沿ってこれをAに相続させるためにしたものであり、抗告人において自らが相続し得ることを前提に、Aに相続させる趣旨で遺産分割協議書の作成をしたものではないと認められるから、これをもって単純承認をしたものとみなすことは相当でない。
「多額の相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、抗告人らが相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と抗告人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」として原審判を取消し、原審判をした家庭裁判所に差し戻しています。
(大阪高決平成10年2月9日)
抗告人らは、他の共同相続人との間で本件遺産分割協議をしており、右協議は、抗告人らが相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきである。しかし、抗告人らが前記多額の相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、抗告人らが相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と抗告人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。
(2) 遺産を取得しなかった相続人による申述も却下された事例
「被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で他の相続人全員と協議し、これを長男に単独取得させる旨を合意し,長男を除く他の相続人らは、各相続分不存在証明書に署名押印している」ことにより、この時点で被相続人の遺産の存在を認識し、自己のために相続の開始があったことを知ったといわざるを得ないとして、相続放棄申述却下審判に対する即時抗告が却下されています。
(東京高決平成14年1月16日)
抗告人らは,被相続人が死亡した直後である平成10年1月○日ころ,被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で他の相続人全員と協議し,これを長男である抗告人Aに単独取得させる旨を合意し,同抗告人を除く他の抗告人らは,各相続分不存在証明書に署名押印しているのであるから,抗告人らは,遅くとも同日ころまでには,被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものであり,抗告人らが被相続人に相続すべき財産がないと信じたと認められないことは明らかである。
抗告人らは,要するに,相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になって初めて,相続の開始を知ったといえる旨を主張するものと解されるが,独自の見解であり,採用することはできない。
そうすると,本件において,抗告人らは,遅くとも,遺産分割協議をした平成10年1月○日ころまでには,被相続人の遺産の存在を認識し,自己のために相続の開始があったことを知ったといわざるを得ないから,民法915条所定の3か月の熟慮期間は,同日の翌日を起算日として計算すべきであり,抗告人らがした平成13年10月○日付けの本件各相続放棄の申述は,明らかに熟慮期間を経過した後にされたものである。
7.相続放棄は誰に相談・依頼するのか
相続放棄の手続きについての相談や依頼ができるのは、司法書士と弁護士に限られます。それ以外の、相続の専門家(行政書士、税理士、FPなど)に相談しても、手続きの依頼をすることはできませんからご注意ください。
裁判所に提出する書類の作成は、司法書士がおこなう主要業務の一つです(司法書士法3条1項4号)。また、弁護士も家庭裁判所での手続きを当然におこなうことができるので、相続放棄の手続きを依頼するなら司法書士と弁護士のいずれかになります(それ以外の専門家といわれる人が、相続放棄の手続きを業として請け負うのは違法です)。
弁護士は依頼者の代理人となって相続放棄の申述をすることができます。司法書士に依頼した場合、司法書士がおこなうのは書類作成および裁判所への提出であり、司法書士が代理人となることはできません。しかし、相続放棄の手続きでは、代理人を立てる必要は無く、司法書士の書類作成によれば全く問題ないのが通常です。
たとえば、相続放棄の手続きは、ほとんどの場合で郵送による書類のやり取りのみで完結します。裁判官や書記官など裁判所の人と直接話をすることは原則としてありませんし、不足書類がある場合などの連絡も書類作成者である司法書士宛てに来るはずですから、代理人がいなくても困ることは全くありません。
そのため、通常の相続放棄の手続きでは、司法書士を書類作成者として申立てをしても不都合が生じることはなく、あえて弁護士に依頼する必要は無いといえるわけです。
8.相続放棄の手続きは高島司法書士事務所へ
司法書士や弁護士であっても誰もが相続放棄の手続きに精通しているとは限りません。相続開始から3か月の期間内の申立てであれば、どこの事務所に頼んでも問題は無いかもしれませんが、被相続人の死亡から長期間が経った場合などの相続放棄では、依頼先によって放棄が受理されるか否かが違ってくることもあるはずです。
「相続放棄の相談室」を運営する松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業時から相続放棄やその他の相続手続きを多数取り扱ってきました。このウェブサイトは司法書士高島一寛が自分で作成しており、すべてのページや記事の作成執筆も自らおこなっています。
また、当事務所ではすべてのご相談に司法書士高島が直接ご対応しておりますし、相続放棄申述の際の上申書作成なども司法書士自身が責任をもっておこなっています。つまり、このウェブサイトを作成している司法書士自身が、実際のご依頼についての書類作成も担当しているわけですから、安心してご相談・ご依頼をいただけるかと思います。
当事務所はウェブサイトやブログなどをご覧いただいた方からのご相談・ご依頼が多いのが特徴です。開業した当初から事務所ホームページを運営しておりますので、10年以上の長期間に渡ってインターネット経由のお客様からのご相談・ご依頼を承ってきたわけです。
そのため、相続放棄の手続きについても「どこに頼んでよいか分からずネットで見て相談した」という方からのお問い合わせを多数いただいております。長年に渡りネット経由での、個人のお客様に対応してきた経験と実績がありますから、新規のご相談・お問い合わせへの対応には自信があります。
当事務所についての更なる情報については、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。その上で、当事務所への相談、依頼をご検討の際は、ぜひお気軽にご連絡ください。